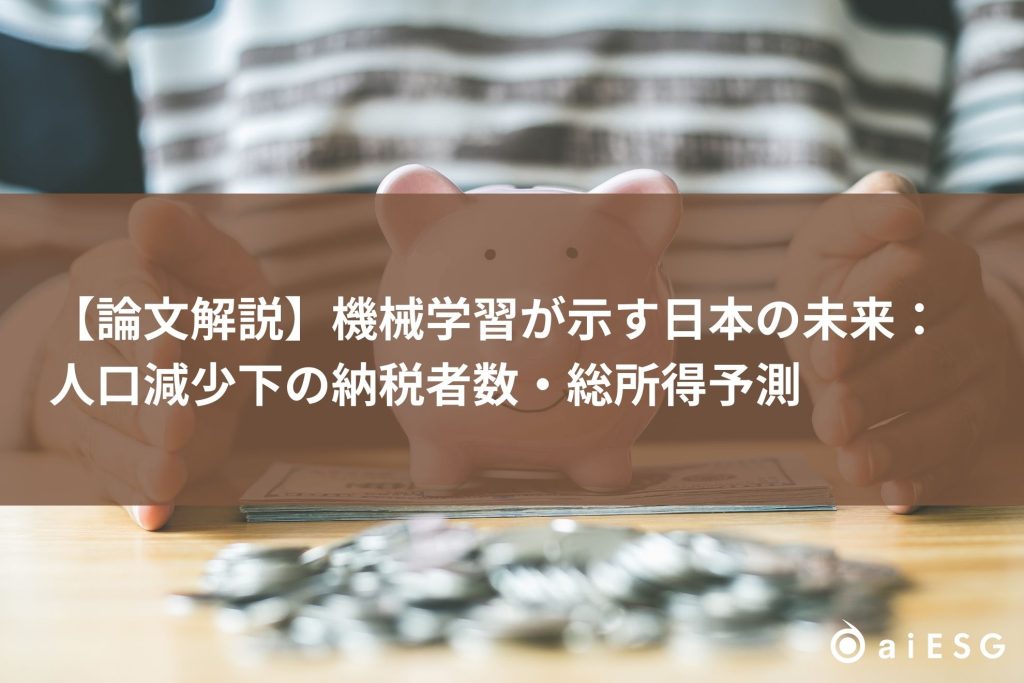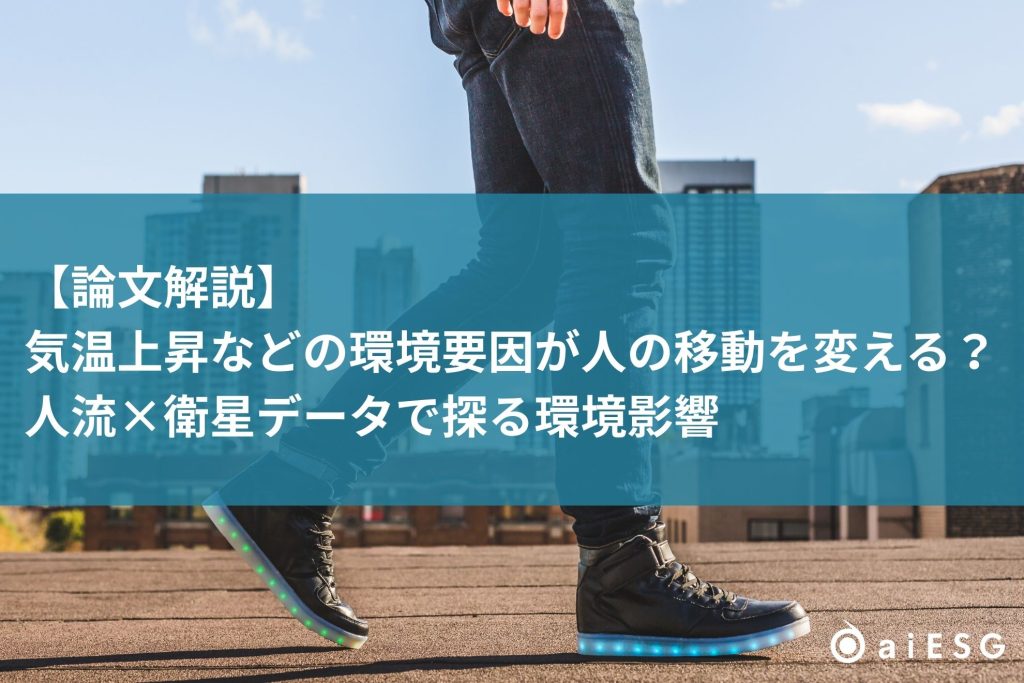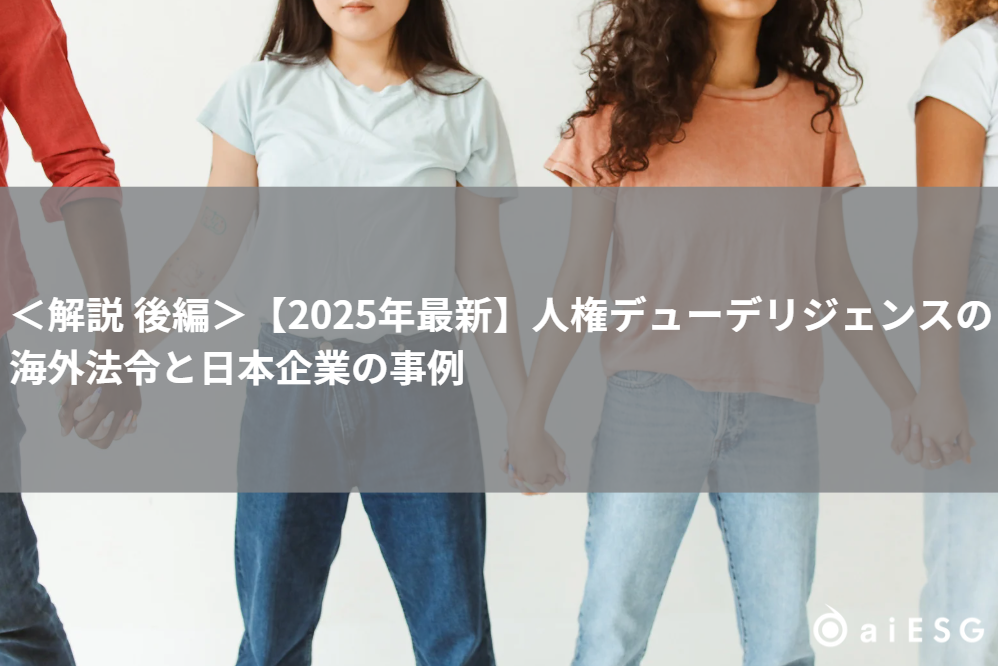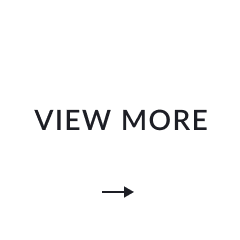INDEX
近年、企業が直面する課題の一つとして、サプライチェーン全体を通じた「人権尊重」が急速に注目を集めています。欧州では、企業に対して人権デューデリジェンス(DD)の実施を義務化する動きが進み、アジアや米国でも関連する規制が強化されてきています。日本も例外ではなく、2022年にビジネスと人権保護に関するガイドラインを策定しました。サプライヤーや協力企業を含むすべての事業活動において、人権尊重の取り組みが経営リスクを軽減し、信頼あるブランドを構築するための新たな基準となりつつあります。
本記事は、人権尊重と企業の対応についてまとめた記事の前編です。日本政府が策定した『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』の重要点について、日本企業が認識するべき関連情報とともにまとめてます。人権尊重はなぜ必要なのか?検討するべき範囲はどの程度なのか?などの疑問をお持ちの日本企業の担当者様にとって有益なヒントを提供します。
1.日本政府の人権尊重ガイドラインの背景と重要性
『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(以下、人権尊重ガイドライン)は、2022年9月に日本政府によって策定されました。国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針、ILO多国籍企業宣言などの国際スタンダードに基づき、日本で事業活動を行う企業が人権尊重の取り組みを具体的かつ分かりやすく理解し、推進することを目的に制作されています。経産省は次いで、実務参照資料を作成することで、包括的な理解を日本企業にしてもらい、国内の人権尊重取組を推進しています。人権尊重ガイドラインの理解を深めるためには、基礎となる国際スタンダードを参照することが推奨されます。
1.1. 国際基準と企業の責任
人権尊重ガイドラインでは、国際基準の一例として、2011年に国連が発表した「ビジネスと人権に関する指導原則」を挙げています。その後、ILO*(国際労働機関) や OECD**(経済協力開発機構) も、国連の指導原則に基づきガイドラインを公表・改訂し、企業が事業活動を通じて人権を尊重することが国際的な標準となりつつあります。日本政府もこの動きを支持し、2020年に「ビジネスと人権に関する行動計画***」を策定。さらに、2022年にはこの行動計画を基に人権尊重ガイドラインを公開しました。
| * 2017年に改訂された「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言(ILO多国籍企業宣言)」は、国家の人権保護義務や企業による人権尊重責任について言及しています。 ** 2018年に採択された「OECD責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンス・ガイダンス」は、すべての国のあらゆる種類の企業や経済界のあらゆる分野に関連するデュー・デリジェンスについての初の参考資料です。このガイダンスは、農業、鉱業、衣料・履物、金融といった個別セクターおよびそのサプライチェーンにおいて、各企業が責任ある企業行動に関するデュー・デリジェンスを実施する際に役立つよう、OECDが既に発行している関連資料を補完するものです。 *** 行動計画の基本は主に5つ挙げられています: (1)政府及び地方公共団体などの「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上; (2)企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上; (3)社会全体の人権に関する理解促進と意識向上; (4)サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備; (5)救済メカニズムの整備及び改善。 |
1.2. なぜ今、人権尊重が求められるのか?
国連指導原則*が示す通り、企業には事業活動を行う主体として、人権を尊重する責任があります。この責任を果たすことは、単に法令遵守や社会的責任の観点にとどまらず、経営面においてもプラスの影響をもたらします。なぜなら、人権尊重の取り組みを進めることで、企業が直面する経営リスクを軽減できるためです。
現在、特に欧州では、企業に人権尊重の取り組みを義務付ける国内法の導入が進んでいます。また、米国でも、強制労働を理由とした輸入差し止め措置を含む、人権侵害に関する法規制の強化が進められています。こうした国際的な動向を踏まえ、多くの日本企業も、ESG**を意識した経営やSDGs16の達成に向けた取り組みを強化しています。特に、アジア地域のサプライヤーを含む関連企業との協力を通じて、労働者の技能向上、労働安全衛生の改善、建設的な労使関係の確立に努め、信頼関係を築いています。これらの「ディーセント・ワーク」***や建設的な労使関係に関する取り組みは、国際基準が求める負の影響の予防・軽減・是正にも貢献します。
さらに、国際的な事業展開をしていない企業であっても、サプライチェーンを通じてグローバルなつながりを持つため、人権尊重の取り組みは不可欠です。また、人権尊重の推進には、企業単独の取り組みではなく、業界全体での協力が求められます。特に、人的・経済的リソースが豊富な企業は、他企業の取り組みを支援する役割も期待されています。ただし、一方的に負担を強いる形での取り組みは、法的リスクを伴う可能性があるため、慎重な対応が必要です。
次項では、人権尊重ガイドラインに記載されている要件について、より詳しく解説します。
| * 国連指導原則は、企業だけでなく各国政府に対しても人権保護のための適切な対応を求めています。つまり、人権尊重の取り組みは、官民が社会全体で取り組むべきであると示しています。 ** 国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)および国連グローバル・コンパクトと連携した投資家イニシアチブである責任投資原則(https://www.unpri.org/download?ac=14736 )は、「責任ある投資」(ESG要因を投資判断やアクティブ・オーナーシップに組み込むための方針と実践)を提唱しており、ESG要因の「Social(社会)」の例として現代奴隷制や児童労働などを挙げています。 *** ILOの定義による「ディーセント・ワーク」とは、やりがいがあり人間らしさが保たれた仕事、具体的には、自由、公平、安全および人間の尊厳が保障されたすべての人のための生産的な仕事を指します。 |
なお、サプライチェーンにおけるESG管理の導入がなぜ重要なのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。本記事では、環境対策だけでなく、人権意識や企業経営のガバナンスといった視点も取り入れる最新の潮流を紹介しています。全3回にわたる構成となっており、それぞれの観点からESG管理の必要性を深掘りしていますので、ぜひご覧ください。
aiESG,【第一回】サプライチェーンが環境および社会に与える影響~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
aiESG,【第二回】学術、ビジネス、市民の三面の視点から主な推進要因とは~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
aiESG,【第三回】ステップ、対応、およびトレンド~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
2.人権尊重ガイドラインの対象企業とは?人権尊重の取り組みの対象範囲
人権尊重ガイドラインには法的拘束力はありません。しかし、日本で事業を行うすべての企業(個人事業主を含む)は、国際基準に基づく人権尊重のガイドラインに従うことが求められています。企業の規模や業種を問わず、適切な対応が期待される点に留意が必要です。
このガイドラインの適用範囲は、自社やグループ会社にとどまらず、国内外のサプライヤーチェーン*やその他のビジネス関係先**(サプライチェーン上の企業や間接的な取引先を含む)にも及びます。そのため、日本企業は人権尊重に向けた取り組みを積極的に推進し、最大限の努力を行うことが推奨されます。
| *「サプライチェーン」とは、自社の製品やサービスのために必要な原材料や資源、設備、ソフトウェアなどの調達・確保に関わる「上流」と、製品・サービスの販売・消費・廃棄に関わる「下流」を指します。 **「その他のビジネス関係先」とは、サプライチェーン上の企業以外でありながら、自社の事業、製品、サービスに関連する他の企業を指します。 |
なお、本ガイドラインは主に以下の構成で成り立っています。特に、ガイドラインの要件を定めているのは「各論3」「各論4」「各論5」であり、企業が実務に活用する際に重要な部分となります。
| 各論1 | はじめに |
| 各論2 | 企業による人権尊重の取組の全体像(総論) |
| 各論3 | 人権方針 |
| 各論4 | 人権DD |
| 各論5 | 救済 |
3.企業が実施すべき人権尊重の取り組み
企業は、人権尊重の責任を果たすために、以下の3つの取り組みを実施することが求められます。
- 「人権方針の策定」(各論3)
- 「人権デューデリジェンス(以下、人権DD)」(各論4)
- 「救済」(各論5):自社が人権に対する負の影響を引き起こしたり、助長したりしている場合に必要
また、これらの取り組みを進めるうえで重要なのは、関係者(ステークホルダー*)との継続的な対話を重ねることです(表1参照)。ステークホルダーの意見を取り入れることで、企業の人権対応の実効性を高めることができます。
| * ステークホルダーとは、企業の活動に影響を受ける、またはその可能性がある利害関係者(個人または集団)を指します。例として、取引先、自社やグループ企業、取引先の従業員、労働組合・労働者代表、消費者、市民団体(NGO)、業界団体、人権擁護者、周辺住民、先住民族、投資家・株主、国や地方自治体などが含まれます。 |
なお、「救済」は、自社の事業・製品・サービスが人権に対して悪影響を及ぼしている場合に適用されます。ただし、該当企業は救済を支援する役割を担うものの、直接的な救済措置を講じる法的義務はありません。

以下では各論を解説します。
3.1.各論3:人権方針
人権方針とは、企業が人権尊重責任を果たすというコミットメント(約束)を企業内外のステークホルダーに向けて明確に示した内容を指します。企業は表2に示される5つの要件を満たす人権方針を社内外に向けて表明することが期待されます。
| 企業のトップを含む経営陣で承認されている |
| 企業内外の専門的な情報・知見を参照したうえで作成されている |
| 従業員、取引先、及び企業の事業、製品またはサービスに直接かかわる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されている |
| 一般に公開され、すべての従業員、取引先及び他の関係者にむけて社内外にわたり周知されている |
| 企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針及び手続きに、人権方針が繁栄されている |
人権尊重ガイドラインでは、人権方針は必ずしも「人権方針」という名称の単独の文書である必要はないとされています。重要なのは、実質的にガイドラインの要件を満たしていることです。ただし、外部に対しては、その内容が人権方針に相当するものであることを明確に示すことが望ましいとも述べられています。
また、人権方針を策定・公表する際には、経営陣の承認を経た企業のコミットメント(約束)を、企業の行動を決定する明確かつ包括的な指針として示すことが極めて重要です。これにより、企業の人権尊重の姿勢を社内外に伝え、実効性のある取り組みにつなげることができます。
3.1.2. 人権方針策定の留意点
人権方針は、企業が人権を尊重するための基本的な考え方を示すものであり、企業の経営理念とも深く関わります。 そのため、策定にあたっては、社内外の多様な視点を取り入れることが重要です。
具体的には、社内の各部門(例:営業、人事、法務・コンプライアンス、調達、製造、経営企画、研究開発)からの知見を集めることに加え、自社業界や原料の調達先、調達国の事情に詳しいステークホルダー(例:労働組合や労働者代表、NGO、使用者団体、業界団体)との対話・協議を行うことが推奨されます。こうしたプロセスを経ることで、企業の実態に即した、より効果的な人権方針の策定につながります。
3.2.各論4:人権DD
デューデリジェンス(DD)は、一度限りの取り組みではなく、循環的なプロセスを通じて継続的に実施されるものです(図1参照)。企業は、自社が影響を及ぼす可能性のある人権課題を把握し、実態に即した方針を策定することが求められます。
特に、グループ会社が異なる国に拠点を持つ場合、その国での人権DDは本社と現地のグループ会社が連携しながら進めることが重要です。ただし、各国の法令を遵守しているからといって、それだけで企業の人権尊重責任を十分に果たしているとは限りません。法令順守と人権尊重は必ずしも同義ではなく、企業は国際的に認められた人権を最大限尊重する取り組みを進める必要があります。

以下では、表1に示される人権DDのプロセス(「負の影響の特定・評価」→「負の影響の防止・軽減」→「取り組みの実効性の評価」→「説明・情報開示」)を参照し、その重要なポイントについて解説します。
「負の影響」の範囲と対応
人権尊重ガイドラインでは、企業が対応すべき「負の影響」について、国際基準(国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針、ILO多国籍企業宣言など)に基づいて定義しています。負の影響は、大きく以下の3つに分類されます。
a.企業が負の影響を引き起こす(Cause)
i.企業の活動自体が、単独で負の影響をもたらす場合。
b.企業が負の影響を助長する(Contribute)
①企業の活動が、他の企業の行動と組み合わさって負の影響を引き起こす場合。
②企業の活動が、他の企業に負の影響を生じさせたり、その影響を促進・動機づけする場合。
c.企業が負の影響に直接関連する(Directly Linked)
企業が負の影響を引き起こしておらず、助長もしていないものの、
取引関係を通じて事業・製品・サービスが人権への負の影響と直接関連する場合。
企業が意識すべき負の影響には、既に発生している影響だけでなく、潜在的な負の影響も含まれます。これらはすべて人権DDの対象となり、企業は次の対応が求められます。
・負の影響が発生する前に、予防策を講じること
・万が一負の影響が発生した場合、その再発防止に努めること
このように、人権DDは単なるリスク管理にとどまらず、企業が持続可能な経営を実現するための重要なプロセスです。各企業が、自社の状況に即した適切な取り組みを進めることが求められます。
人権DDの第一歩:負の影響の特定と評価
人権DDの最初のステップは、企業が関与する、または関与する可能性のある人権への負の影響を特定し、評価することです(図2参照)。この特定・評価の過程では、従業員、労働組合・労働者代表、市民団体、周辺住民などのステークホルダーとの対話が極めて有益です。
また、人権への負の影響を評価する際は、特に弱い立場に置かれやすい個人や、社会的に排除されるリスクが高い集団・民族に属する個人への潜在的な負の影響に十分配慮することが求められます。さらに、企業は直接取引のない2次取引先以降においても、人権への負の影響を防止・軽減する責任を負うことが重要です。

人権DDは、一度実施すれば完了するものではなく、常に変化する人権状況に対応するために、定期的な評価と見直しが必要です。企業は、初回の評価にとどまらず、人権への影響を繰り返し評価し、徐々に掘り下げていくことが求められます。
対応の優先順位は、人権への負の影響の深刻度に基づいて判断され、深刻度の高いものから優先的に対応することが求められます。それらの深刻度は、人権への負の影響の規模、範囲、救済困難度という3つの基準を踏まえて判断することを人権尊重ガイドラインは示しています。
- 負の影響の防止・軽減
企業は、人権尊重の責任を果たすために、自社の事業活動において人権への負の影響を引き起こしたり、助長したりしないよう努めることが求められます。また、すでに発生している負の影響については、適切な措置を講じることで防止・軽減することが必要です。
人権尊重の取り組みは、結果として企業の経営リスクの低減につながる可能性もありますが、主な目的は人権への負の影響の防止と救済であることを認識することが重要です。
企業が人権への負の影響に対応するために検討すべき措置は、大きく2つのケースに分けられます。
①自社が人権への負の影響を引き起こしている、または助長している場合
企業は、負の影響を防止・軽減するために、以下のような措置を講じる必要があります。
a.負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を確実に停止し、
将来的に同様の影響が再発しないようにする。
例:製品設計を見直し、有害物質の使用を削減・廃止する。
b.契約や法的な理由で即時に停止が難しい場合は、活動停止に向けた工程表を作成し、
段階的に停止を求める
②自社の事業等が人権の負の影響に直接関連している場合
自社が直接的に負の影響を引き起こしていなくても、関連する事業、製品、
サービスを通じて影響が生じている場合には、負の影響を防止・軽減するための
対応が求められます。
企業は状況に応じて、影響を及ぼしている企業に対し、影響力を行使する、
または影響力を強化し支援するなどの取り組みを行うべきです。
取引停止は最終手段として考慮
負の影響を軽減するための措置として「取引停止」がありますが、人権尊重ガイドラインでは、取引停止は最終手段として慎重に検討することが求められています。
まずは、サプライヤーや関連企業との関係を維持しつつ、負の影響を防止・軽減する努力を優先すべきです。なぜなら、取引停止は自社と負の影響との関係を解消する手段にはなりますが、影響そのものを解決するわけではないためです。
また、取引停止が新たな人権リスクを生じさせる可能性もあります。例えば、
- 取引停止により、負の影響の監視が困難になる。
- 相手企業の経営が悪化し、従業員の雇用が脅かされる。
このようなリスクを考慮し、企業は取引停止を検討する前に、まずはパートナー企業と協力しながら改善策を講じることが重要です。
- 取り組みの実効性評価と継続的な改善
企業は、自社が人権への負の影響の特定・評価・防止・軽減に効果的に対応しているかを定期的に評価し、その結果をもとに継続的な改善を図ることが求められます。
評価を行う際には、広範な情報を収集し、可能な限り適切な指標に基づいて分析することが重要です。人権への影響は数値化が難しい場合もあるため、質的・量的両面から適切な指標を設定し、多角的に評価することが求められます。
また、実効性評価を社内の関連プロセスに組み込むことも有効です。 例えば、従来から実施している環境監査や安全衛生監査、現地訪問の手続きに人権の視点を追加することで、人権への配慮を企業活動の一部として継続的に推進することができます。
- 人権尊重の責任と情報開示の重要性
企業には、人権尊重の責任を果たしていることを説明し、適切な情報を開示することが求められます。人権尊重に関する情報公開は、たとえ人権侵害の事例が特定された場合であっても、企業価値を損なうものではありません。むしろ、透明性を確保し、改善に取り組む姿勢を示すことが、企業価値の向上につながります。
情報開示のポイント
情報開示に際し、企業は以下の点に留意する必要があります。
- 人権デューデリジェンス(DD)に関する基本情報の提供
- 企業が負の影響にどのように取り組んでいるか、プロセスや方針を明確に説明する。
- 重大な負の影響リスクへの対処方法の説明
- 企業が直面する可能性のある重大な人権リスクに対し、どのように防止・軽減策を講じているかを示す。
- 特定の人権影響事例への対応の透明性
- 企業が関与した特定の人権影響事例について、どのような対応を行ったのかを明示し、その適切性を評価できる内容とする。
このように、単なる情報提供にとどまらず、企業の取り組みが適切であることを示し、ステークホルダーとの信頼関係を構築することが重要です。
3.3.各論5:救済
救済とは、人権への負の影響を軽減・回復すること、またはそのためのプロセスを指します。 企業が自社の活動によって人権への負の影響を引き起こしたり、助長していると認められた場合、救済措置を実施するか、その実施に協力する必要があります。
一方で、企業の事業や製品・サービスが負の影響と直接関連しているものの、影響を引き起こしていない場合には、企業が救済を支援する役割を担うことは求められますが、実際に救済を実施する義務までは負いません。
時には国家が救済手段を提供している場合があります。具体的には、司法的手段としての裁判所での訴訟、非司法的手段として、厚生労働省の個別労働紛争解決制度、OECD多国籍企業行動指針に基づく外務省・厚生労働省・経済産業省の連絡窓口(ナショナル・コンタクト・ポイント)などが挙げられます。しかし、これらの手段が常に有効とは限りません。そのため、企業は独自に「苦情処理メカニズム」を設けることが望ましいとされています。とが望ましいです。
苦情メカニズムの役割と設計のポイント
「苦情処理メカニズム」とは、影響を受けるステークホルダーがその存在を認識し、信頼を持って利用できる仕組みを指します。企業は、苦情に迅速かつ適切に対応し、直接的な救済の実現を目指すことが重要です。
企業が取り組むべきポイントは以下の通りです。
- 苦情処理メカニズムの設置または参加
- 自社で苦情処理メカニズムを設置する
- 業界団体等が提供する苦情処理メカニズムに参加する
- 幅広いステークホルダーが利用可能であること
- 自社の従業員だけでなく、取引先の従業員、地域住民など、影響を受け得るすべてのステークホルダーが利用できるようにする。
- 国際的な人権基準に対応すること
- 苦情処理メカニズムは、国内問題にとどまらず、国際的に認められた人権に関する問題にも対応できるように設計することが望ましい。
| 正当性 | 苦情処理メカニズムが構成に運営され、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーから信頼を得ていること |
| 利用可能性 | 苦情処理メカニズムの利用が見込まれる全てのステークホルダーに周知され、例えば使用言語や識字能力、報復への恐れ等の視点からその利用に支障があるものには適切な支援が提供されていること |
| 予測可能性 | 苦情処理の段階に応じて目安となる所要時間が明示された、明確で周知された手続きが提供され、手続きの種類や結果、履行の監視方法が明確であること |
| 公平性 | 苦情申立人が、公正に、十分な情報を提供された状態で、敬意を払われながら苦情処理メカニズムに参加するために必要な情報源、助言や専門知識に、合理的なアクセスが確保されるよう努めていること |
| 透明性 | 苦情申立人に手続の経過について十分な説明をし、かつ、手続きの実効性について信頼を得て、問題となっている公共の関心に応えるために十分な情報を提供すること |
| 権利適合性 | 苦情処理メカニズムの結果と救済の双方が、国際的に認められた人権の考え方と適合していることを確保すること |
| 持続的な学修源 | 苦情処理メカニズムを改善し、将来の苦情や人権侵害を予防するための教訓を得るために関連措置を活用すること |
| 対話に基づくこと | 苦情処理メカニズムの制度設計や成果について、そのメカニズムを利用することが見込まれるステークホルダーと協議し、苦情に対処して解決するための手段としての対話に焦点を当てること |
4.結論
現代の企業経営において、「人権尊重」は単なる社会貢献の一環ではなく、競争力の維持・向上や経営リスクの軽減に直結する重要な課題となっています。本記事で紹介した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」は、法的拘束力こそ持たないものの、企業の信頼性を高めるための必須基準として位置づけられています。
今後、日本企業がこのガイドラインを理解し、実践へと移すためには、国際基準に基づく具体的な対応策の策定や、業界全体での協力体制の構築が不可欠です。これにより、企業は単に法規制を遵守するだけでなく、持続可能な事業運営の基盤を確立することができます。
後編では、人権デューデリジェンスの海外法令と日本企業の対応を解説いたします。
aiESGは、サプライチェーンのESG影響を製品・サービスレベルで分析するツールを国内で初めて開発しました。このaiESG分析では、企業が生産する製品やサービスに関連するサプライチェーン上の人権への影響(社会的・環境的影響を含む)を定量的に評価し、概算値を提供します。これにより、企業はサプライチェーン全体のリスクを可視化し、より適切なESG対応を進めることが可能になります。
人権尊重の取り組みを強化し、持続可能な企業経営を目指すために、ぜひaiESGの分析ツールをご活用ください。
お問い合わせはこちら:https://aiesg.co.jp/contact/
関連するaiESG記事:
【第一回】サプライチェーンが環境および社会に与える影響~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【第二回】学術、ビジネス、市民の三面の視点から主な推進要因とは~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【第三回】ステップ、対応、およびトレンド~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【解説】欧州企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の概要と修正内容
【解説】欧州企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の理解:人権・環境に及ぼす悪影響を評価義務化
【解説】非財務情報開示における社会面の重要性
参考資料:
経済産業省(2023)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」
経済産業省 (2022) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
外務省(2021)「ビジネスと人権」に関する取組事例集
法務省(2020)「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)について
OECD(2018)「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」
国際連合(2011)「ビジネスと人権に関する指導原則」