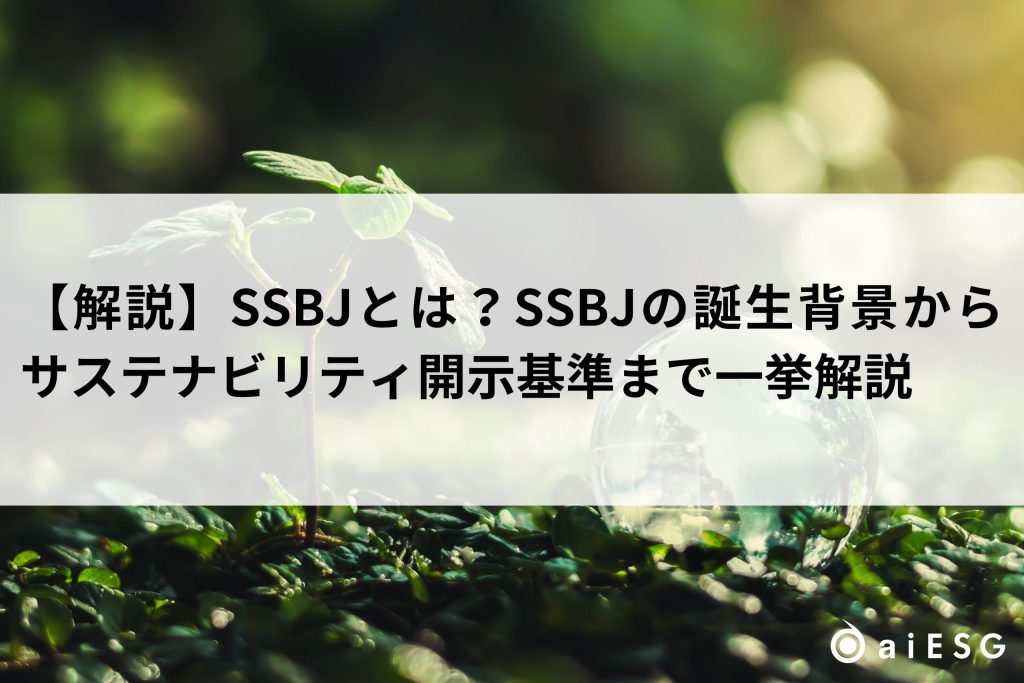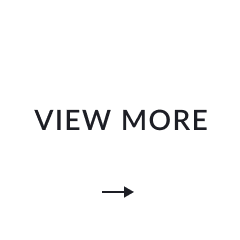INDEX
はじめに
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは持続可能性に関連する基準や情報開示の枠組みを開発することに焦点を当てた日本の組織です。企業が非財務情報について開示する際のガイドラインとなる日本版サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の開発に取り組んでいます。2024年3月にはSSBJ基準の公開草案が公表され、2025年3月5日にSSBJ基準の確定版が公表されました[1]。確定版サステナビリティ開示基準はこちらからご覧ください。
サステナビリティ基準委員会
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html
SSBJ確定基準の公表に合わせて、情報開示体制・開示内容の大幅な変更、関連法令の整備、ESG投資を促進するプラットフォームの発展など投資環境が大きく変化することが予想されます。こうした企業開示とサステナブルファイナンスの新しい動きに対応するためには、SSBJ基準を深く理解することが求められるでしょう。本レポートではSSBJの基礎知識・背景からSSBJ基準の要点までわかりやすくまとめて解説いたします。
サステナビリティ開示基準の誕生背景
気候変動や社会問題に対する関心が世界的に高まる中で、企業の社会持続性への取り組みから企業価値を判断し投融資を行うESG投資やサステナブルファイナンスが盛んになりつつあります。
一方サステナビリティ情報を代表とする非財務情報の開示に関しては、これまでTCFD・TNFD・ESRS・GRIなど異なるサステナビリティ基準が乱立し企業や投資家の混乱を招いていました。
こうした状況を打開するため、2021年にISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が設立されました。ISSBは国際的に統一されたサステナビリティ開示基準を作成し、関連情報の透明性と信頼性を向上させるために活動しています。日本においても国際基準との整合性を確保しつつ日本企業の実態に沿った開示基準を作成するために、2022年7月にSSBJが設立されました。
ISSBについてはこちらの解説記事からご覧ください。
【解説】ISSB ~サステナビリティ開示のグローバル・ベースライン~
https://aiesg.co.jp/topics/report/2301130_issb/
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは
SSBJは日本版サステナビリティ開示基準を作成する組織です。日本企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する情報を開示する際の透明性を担保できる基準作成を主な目的としています。
日本にはすでに地球温暖化対策推進法など非財務情報開示に関連する独自の法規制があり、ISSB基準と独自の法規制の間で整合性をとることが求められていました。またISSB基準はグローバル企業向けに設計されているため日本の中堅・中小企業への適用には負担が大きいという課題がありました。
こうした事情からISSB基準をそのまま適用せずに、「国際基準との整合性」と「国内実情との適合性」の二つを両立できるようなサステナビリティ開示基準の作成に取り組んでいます。
| 項目 | 内容 |
| 設立日 | 2022年7月 |
| 所属 | FASF(公益財団法人財務合計基準機構)内の組織 |
| 活動内容 | ・日本版サステナビリティ開示基準の作成 ・国際サステナビリティ開示基準(IFRS)作成への貢献 |
| 開発方針 | IFRSとの整合性を保ちつつ日本企業の要求事項も考慮 |
表1 SSBJの概要([2]より筆者作成)
組織構造
SSBJはFASF(公益財団法人財務会計基準機構)内に所属する委員会の1つです(図2)。 FASFは経済団体連合会・日本公認会計士協会など10の民間団体により設立された公益財団法人であり、公正な会計基準・サステナビリティ報告基準の調査研究及び開発などを目的としています [3]。サステナビリティ情報開示のニーズが高まる中で財務情報以外の企業開示にも焦点を当てるために、SSBJが2022年7月に設立されました。
図1 FASFの組織構造([4]より引用)
SSBJは13名の委員と8名の研究員、2名のディレクターから構成されています[5][6]。委員はASBJ(企業会計基準委員会)の委員・大学・監査・金融・製造業など幅広い業界から構成されています。
活動内容
SSBJの役割は大きく分けて以下の2つです[2]。
・サステナビリティ開示基準(日本基準)の開発
・国際的サステナビリティ開示基準(IFRS)の開発への貢献
⑴サステナビリティ開示基準(日本基準)の開発
SSBJにおけるもっとも重要な役割は日本版サステナビリティ開示基準の開発です。
2014年に金融庁が「責任ある機関投資家の諸原則」を公表したことや2015年にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRI(国連責任投資原則)に署名したことがきっかけとなり、日本においてもサステナブル投資が年々盛んになっています(図2)。
図2 日本におけるサステナブル投資残高の推移 ([7]より引用)
日本企業の競争力と価値を高めるためには、各企業がサステナブルファイナンスを積極的に活用することが重要です。サステナブル投資が日本企業に対してより積極的に行われるためには、企業が透明性・信頼性の高いサステナビリティ情報を開示する必要があります。
日本企業のサステナビリティ情報の開示の促進と透明性・信頼性の確保を目的として、SSBJはサステナビリティ情報など非財務情報を開示する際のガイドライン「サステナビリティ開示基準」の開発に取り組み、2025年3月5日に確定版のサステナビリティ開示基準を公表しました。
サステナビリティ開示基準を作成する際には、海外からのサステナブル投資資金を日本に呼び込むためISSBが策定する国際的サステナビリティ開示基準(IFRS)との整合性を担保しつつ、既存の諸法律・会計基準と齟齬がないようにするなど日本企業の実態に合うように調整しています[8]。
⑵国際的サステナビリティ開示基準(IFRS)の開発への貢献
SSBJのもう一つの副次的な役割としてIFRSの開発への貢献があげられます。
SSBJが作成するサステナビリティ開示基準は基本的にISSBが作成するIFRSを、国際的な整合性を保ちつつ日本企業に合わせて調整したものになります。そのためIFRSの開示基準としての完成度がSSBJが作成する日本基準の完成度に直結することになります。
また日本のサステナビリティに対する考え方をIFRSに反映し、サステナビリティ基準開発における日本の存在感及び影響力の向上を図ることは日本市場にとって大きく資することにつながります。
SSBJでは具体的なIFRS開発の貢献として
・ISSBの公開草案及び情報要請などに対してコメント・レターを提出
・ISSBにおいて設置されている「サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム」
(SSAF)などの国際会議においての意見発信
などの取り組みを行っています[2]。
SSBJ基準の構造・開発方針
前述の通りSSBJ基準はISSB基準をベースとして日本に合うように改良・調整されています。図3が示すようにISSB基準とSSBJ基準は基本的には同じ構造ですが、開示基準と開示項目を完全に二分している点で大きく異なります。
SSBJ基準は
・ユニバーサル基準
・テーマ別基準
の二つに分けて作成されています(図3)。
さらにテーマ別基準は
・一般開示基準 (サステナビリティ開示テーマ別基準第一号)
・気候関連開示基準(サステナビリティ開示テーマ別基準第二号)
の二つに分けて作成されています(図3)。
図3 ISSB基準(IFRS)とSSBJ基準の構造比較 ([9]より引用)
ここで「基本的事項を定めた部分」はサステナビリティに関連する情報開示をする際の規則や手順などを、「コア・コンテンツ」はサステナビリティ情報の中で開示すべき事項を指します[9]。 開示の作成に関する基準と開示の内容に関する基準を別々に記述することで、わかりやすさを向上させた点がSSBJ基準の大きな特徴であるといえます。
SSBJ確定基準はISSB基準を基に作成されていますが、日本の諸制度や企業との整合性を保つために、一部の項目ではISSB基準に代わってSSBJ基準独自の取り扱いを選択することができます[10]。
SSBJ基準を適用した場合にSSBJ基準独自の取り扱いを選択しなければ、開示情報がISSB基準にも準拠したことになります。ただしSSBJ基準独自の取り扱いを選択した場合には開示情報がISSB基準に準拠しているかについて別途確認が必要です。
適用基準(ユニバーサル基準)
以下ではSSBJ基準を構成する三つの基準について、概要と重要な点を抜き出してそれぞれ解説します。
適用基準(ユニバーサル基準)はサステナビリティ情報の開示を作成する際の規則や他二つの開示基準に対する補足などを記した、基本的な事項を定めた部分です。具体的には企業開示における表示の仕方・情報の記載場所、開示する情報が満たすべき条件などが示されています。本文はこちらからご覧になれます。
適用基準案
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2024ed01_02.pdf
重要な論点① サステナビリティ開示情報に必要な裏付け
適用基準では企業が開示資料を作成する際に提示するガイダンスの情報源として
「適用しなければならない」
「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」
「参照し、その適用可能性を考慮することができる」
の3つの情報源があると分類し、こうした情報源をもとに、企業開示において提示する事柄を裏付けしなければならないとしています[11]。 こうした情報源の分類は気候関連開示基準(テーマ別基準②)においても用いられています。
(a)サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別
企業の見通しに影響を与えると見込まれるサステナビリティ関連の開示内容は、その信頼性を担保するために以下の情報源を適用・参照しなければなりません(表2)。
| 適用しなければならない | SSBJ基準 |
| 参照しその適用可能性を考慮しなければならない | SASBスタンダード |
| 参照しその適用可能性を考慮できる | IFRS・IFRSガイダンス 「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」 「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」 ・他基準設定主体による直近の公表文書 ・同産業or地域の企業がすでに識別しているサステナビリティ関連情報 |
表2 サステナビリティ関連の開示内容を識別するための情報源([11]より筆者作成)
2025年3月に公開されたユニバーサル基準では、SSBJ基準のほかにSASBスタンダードとCDSBフレームワークを取り上げています。この2つの基準はSSBJ基準適用後に企業開示を作成する際も使用できるので注目すべきでしょう。
SASBスタンダードとは2018年に米国サステナビリティ会計基準審議会が公開したサステナビリティ情報開示のためのフレームワークです。世界合計で2500社を超える企業が採用していて[12]、 業種毎に企業の財務パフォーマンスに影響を与える可能性が高いサステナビリティ課題を特定しているのが特徴です。
CDSBフレームワークとは環境情報を財務情報に統合することで環境にかかわる投資家の意思決定を支援することを目的に作成されたESG開示基準です[13]。 気候変動のみならず、水・生物多様性・森林・土地など幅広い環境問題を扱っているのが特徴です。
SASBについての解説はこちらの記事からご覧ください。
【解説】ESG情報開示基準 SASBスタンダードとは?(前編)SASB概要
https://aiesg.co.jp/topics/report/2301025_sasb1/
(b) (a)(サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別)に関連する重要性がある情報の識別
サステナビリティ関連の事柄に付随し、企業の見通しに影響を与えると思われる情報については、原則SSBJ基準の内容から識別をする必要があります。しかしSSBJ基準内に具体的に適用できる内容がない場合は以下の情報源を適用・参照しなければなりません(表3)[11]。
| 参照し適用可能性を考慮しなければならない | SASBスタンダード |
| 参照し適用可能性を考慮できる | CDSBフレームワーク適用ガイダンス GRIスタンダード *1 ESRS *1 ・他基準設定主体による直近の公表文書 ・同産業or地域の企業がすでに識別しているサステナビリティ関連情報 |
表3 重要性がある情報を識別するための情報源([11]より筆者作成)
*1 はSSBJ基準と矛盾しない範囲での適用・参照が認められる
ここではSASBスタンダード・CDSBフレームワークのほかにGRIスタンダード・ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の参照・適用が認められています。
GRIスタンダード・ESRSについては以下の記事で解説しています。
【解説】GHGからESGへ:国際動向とより広範なサステナビリティ考慮へのシフト
https://aiesg.co.jp/topics/report/240529_securities-report/
【解説第一回】ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の概要
https://aiesg.co.jp/topics/report/2301208_esrs/
重要な論点② 比較情報の提示義務
SSBJ基準を適用して開示資料を作成する際に記載する数値は、すべて当年度の数値だけでなく前年度の数値を記載し比較情報として提示しなければなりません[11]。ただし各企業が任意でサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合、または初めてSSBJ基準を適用する年次の報告においては、その旨を開示したうえで以下に挙げる二つの経過措置を適用することができます。
・比較情報を開示しない
・気候関連開示基準に準拠したうえで気候関連のリスク及び機会のみの開示
一般開示基準(テーマ別基準①)
一般開示基準では気候問題に直接関連しないサステナビリティ情報の開示内容(=コア・コンテンツ)について定めています。本文はこちらからご覧になれます。
一般開示基準
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250305_02.pdf
重要な論点③ 一般開示基準のコア・コンテンツとは?
一般開示基準を適用する開示資料においては原則、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び目標の4つの構成要素(=コア・コンテンツ)について開示する必要があります。以下では4つの構成要素について概要を説明します[14]。
図4 コア・コンテンツの概略図([14]よりナプキンAIを用いて作成)
⑴ガバナンス の項目においては、サステナビリティ関連の事柄を監督するために企業が用いるガバナンスのプロセスを利用者が理解できるようにすべきであると指摘されています。具体的にはサステナビリティ関連の事柄に関する監督責任の所在、サステナビリティ情報の取得頻度・方法、サステナビリティ関連の事柄に対する監督者の考え方、経営者の役割が他機関に委任されているかどうかなどを開示する必要があります。
⑵戦略 の項目においては、サステナビリティ関連の事柄に関する企業の戦略を理解するために以下の情報を開示しなければならないと定めています。
・開示目的
・サステナビリティ関連のリスク及び機会 *2
・ビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響
・財務的影響
・戦略および意思決定にあたる影響
・レジリエンス *3
*2 適用基準の項に記載した「企業の見通しに影響を与えると見込まれるサステナビリティ関連の事柄」を指しています。この事柄を開示する必要があり、さらに開示する際に「短期」「中期」「長期」を定義したうえで「影響が生じるまでにかかる期間」を同時に示さなければなりません。
*3 レジリエンスとは「サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対応する企業の能力」とされています。企業はサステナビリティ関連のリスクに関連する戦略及びビジネスモデルのレジリエンスに関する定性的評価を求められます。
⑶リスク管理 の項目については、企業のサステナビリティ関連のリスクと機会及び全体的なリスク管理プロセスを理解し・評価することが目的であると述べられています。具体的に開示しなければならない情報として、リスクの優先順位・評価をするための情報、シナリオ分析を用いている場合にはその利用方法に関する情報などを開示する必要があります。
⑷指標及び目標 の項目については、サステナビリティ関連の取り組みに関する企業のパフォーマンスおよび企業が設定した目標の達成に向けた進捗を利用者が理解できるようにすることが目的であると述べられています。企業がサステナビリティ情報を開示する際には、適用した基準が要求している指標やサステナビリティ情報の測定・評価に用いた指標を開示しなければなりません。
気候関連開示基準(テーマ別基準②)
気候関連開示基準では気候問題に関連する企業開示の内容について定めています。気候関連開示基準においても一般開示基準と同様、気候関連開示基準のコア・コンテンツについて重点的に述べられています[16]。 本文はこちらからご覧ください(再掲)。
気候関連開示基準
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250305_03.pdf
気候関連開示基準を適用する企業開示においても一般開示基準と同様、気候関連の企業開示に関するガバナンス・戦略・リスク管理・指標及び目標の4項目について開示する必要があります。これらの開示を通して、企業がどのように気候関連のリスク及び機会を監督・評価し、関連する戦略及び進捗を利用者が理解できるようにしなければなりません。
コア・コンテンツの基本的な構成は一般開示基準と同様であるので、本レポートでは一般開示基準と大きく異なる要素をピックアップして解説いたします。
重要な論点④ 気候関連のシナリオ分析(戦略)
気候関連開示基準を適用する開示資料は、気候関連のシナリオ分析に基づいて、気候関連の変化や不確実性に対応する企業の能力(=気候レジリエンス)を評価する必要があります。ただし、気候レジリエンスは報告期間ごとに評価しなければなりませんが、気候関連のシナリオ分析については少なくとも戦略計画サイクルに沿って更新すれば良いとしています。
気候関連のシナリオ分析を実施した際には以下の事項を開示しなければなりません。
・シナリオ分析に用いたインプットに関する情報
・分析の前提となる仮定
・気候関連のシナリオ分析を実施した報告期間
同様に、気候レジリエンスを評価した際には以下の事項を開示しなければなりません。
・気候関連のシナリオ分析の結果が企業の戦略・ビジネスモデルの評価に与える影響
・気候レジリエンスの評価において考慮された重大な不確実性の領域
・気候変動に対して短・中・長期にわたり戦略・ビジネスモデルを調整する企業の能力
重要な論点⑤ 温室効果ガス排出の絶対総量の開示(指標及び目標)
開示資料はまた、報告期間中に生成した温室効果ガス排出の絶対総量について
・スコープ1温室効果ガス排出…企業が直接的に排出する温室効果ガス
・スコープ2温室効果ガス排出…企業が間接的に排出する温室効果ガス
・スコープ3温室効果ガス排出…原材料の仕入れ時・販売後に排出される温室効果ガス
の3つの区分に分けて開示しなければなりません。またこれらの温室効果ガス排出の測定は原則GHGプロトコル(2004年)に従って行わなければなりません。特にスコープ3の温室効果ガスはサプライチェーンをさかのぼって計算する必要があり、取り扱いが難しいサステナビリティ情報となっています。
スコープ3温室効果ガスについてはこちらの記事で解説しています。
【解説】SSBJ(サステナビリティ基準委員会)の審議動向 ~日本におけるScope3の開示基準について~
まとめ
企業規模に応じて義務化が検討されていることもあり、SSBJ確定基準が公開されれば多くの企業が企業情報開示にSSBJ基準を適用していくと考えられます。SSBJ基準について理解を深めいち早く適用することが、より円滑な資金調達を受けるために必要となるでしょう。
aiESGでは製品のサプライチェーンに関するESG分析サービスを提供しています。SSBJ基準やその他ESG関連基準など、企業開示について関心・疑問点などございましたらぜひお気軽にご相談ください。
参考文献
[1] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250305_04.pdf
[2] https://www.ssb-j.jp/jp/list-ssbj_2.html
[3] https://www.fasf-j.jp/jp/fasf-overview.html
[4] https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20221102/03.pdf
[5] https://www.ssb-j.jp/jp/list-ssbj_2/staff.html
[6] https://www.ssb-j.jp/jp/list-ssbj_2/boardmen.html
[7] https://japansif.com/2023survey-jp.pdf
[8] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/middle_plan_20221124.pdf
[9] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2024ed01_01.pdf
[10] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20240628.pdf
[11] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250305_01.pdf
[12] https://sasb.ifrs.org/about/global-use/
[13] https://www.cdsb.net/sites/default/files/sasb_cdsb-tcfd-implementation-guide_japanese.pdf
[14] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250305_02.pdf
[15] https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250305_03.pdf
[16] https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20240326/03.pdf
関連記事
【解説】ISSB ~サステナビリティ開示のグローバル・ベースライン~
【解説】ESG情報開示基準 SASBスタンダードとは?(前編)SASB概要
【解説】GHGからESGへ:国際動向とより広範なサステナビリティ考慮へのシフト
【解説第一回】ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の概要