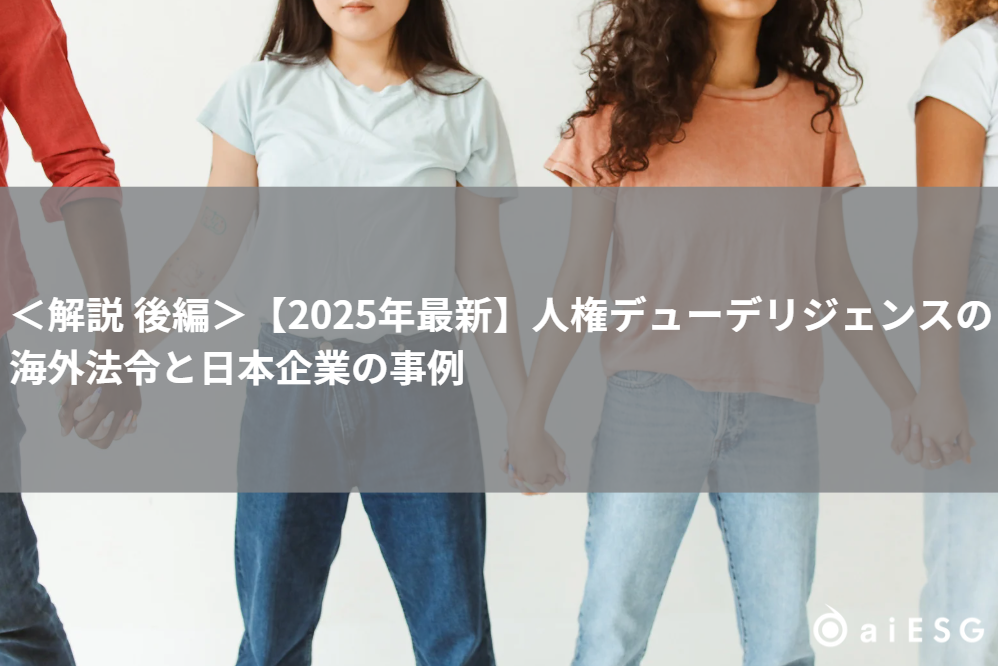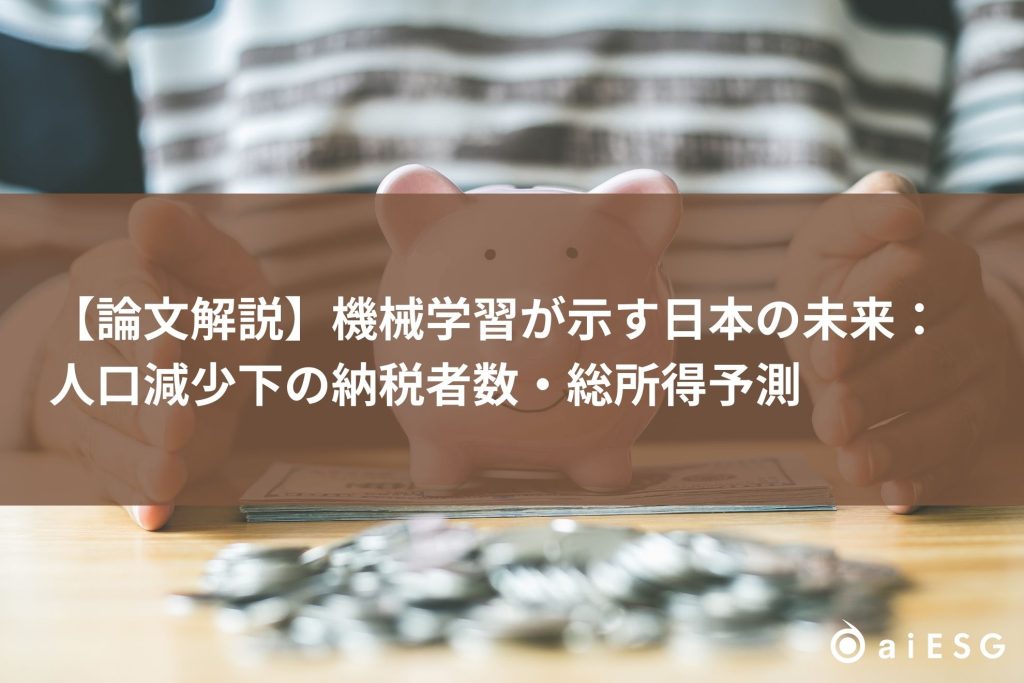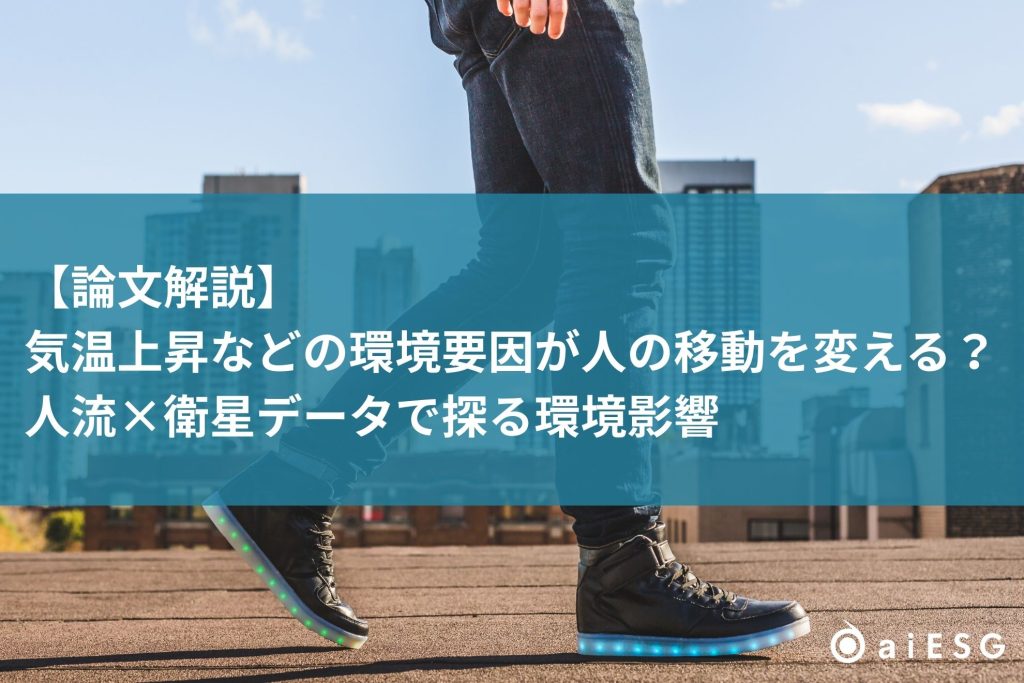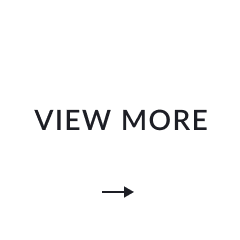INDEX
前編の記事では、日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」について、その背景や必要性を解説しました。後編では、具体例を交えて、人権デューデリジェンス(DD)に関する海外法令と日本企業の対応を紹介します。特に、サプライチェーンおよびバリューチェーンにおけるリスク評価と対策に焦点を当て、企業が直面する課題とその解決策を考察します。
企業がグローバルサプライチェーンを管理する上で直面する課題は、規制の強化だけではありません。取引先の多層化やデータ管理の複雑さも大きな要因となっています。近年では、サプライチェーンの可視化が進み、一次サプライヤーにとどまらず、二次・三次サプライヤーまで管理が求められる傾向にあります。さらに、バリューチェーン全体のリスク管理手法も多様化しており、AIやブロックチェーンなどのテクノロジーを活用したリスクモニタリングの重要性が高まっています。
この記事のポイント
- 海外の人権デューデリジェンス法制化:各法の内容や、自社が関係しているのかが確認できる
- 日本企業の人権デューデリジェンス事例:国内の先進事例や課題が分かる
海外の人権デューデリジェンス法制化【EU・米国の最新規制】
近年、世界各国で企業に対する人権・環境デューデリジェンス(HREDD*)の法制化が進んでいます。
欧州と米国では、大まかに次のような傾向があります。
欧州:企業に対し人権デューデリジェンスの実施および情報開示を義務付ける法整備が進み、バリューチェーン全体に対する責任が強化
米国:米国では、強制労働によって製造された製品の輸入を規制する法律が適用され、特定地域や業界に対する監視が強化。さらにカリフォルニア州では、企業に対し自社事業およびサプライチェーンにおけるリスク対応についての開示や監督機関への報告を義務付ける法制度が導入されています。
このように、人権デューデリジェンスに関する規制は国や地域によって異なりますが、企業のサプライチェーン全体におけるリスク管理の強化を求める動きは共通して加速しています。以下に2025年時点で施行または施行予定の主要な人権デューデリジェンス関連法規制を一覧にまとめました。
| 地域 | 法令 | 概要 | 影響を受けるであろう日本企業 |
| EU | 企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD) | 自社・子会社・確立したビジネス関係のあるバリューチェーンにおける人権・環境リスクのデュー・ディリジェンス実施と開示を義務付ける。また、事業体が関与する国・地域のガバナンス状況も考慮する。 | 欧州で事業を展開する製造業、商社、金融機関など |
| ドイツ | サプライチェーン・デューデリジェンス法 | 一定規模以上の在独企業は、サプライチェーンにおける人権・環境リスクのデュー・ディリジェンス実施と開示が義務付けられる。強制労働などの人権リスクや関連環境リスクの査定・予防措置が求められ、一次サプライヤーが対象、間接サプライヤーはリスク認識時のみ監査対象。 | ドイツ市場と取引のある製造業、部品供給企業など |
| フランス | 注意義務法 | サプライチェーンにおける人権・環境デュー・ディリジェンスを規定し、対象企業に計画策定・実施・開示を義務付ける。計画にはリスク特定と重大侵害防止措置を含める必要がある。特に親会社の海外子会社やサプライチェーンの影響回避を重視。 | フランスで事業を展開する企業 |
| 米国 | ウイグル強制労働防止法(UFLPA) | 新疆ウイグル自治区産品の輸入を原則禁止し、強制労働産品と推定する。ただし、輸入者がUFLPA戦略を順守し、強制労働でないと「明白で説得的な証拠」を示せば例外的に認められる。特定リストの企業製品も同様に輸入禁止対象。 | 米国に製品を輸出する企業、特に衣料、電子部品、農産物関連企業 |
| 米国(カリフォルニア州) | サプライチェーン透明化法 | 一定規模以上の製造・小売業者に対し、サプライチェーンにおける人身取引や奴隷労働リスクへの対処状況の開示を義務付けている。 | カリフォルニア州で事業展開する企業 |
2024年に最終合意された企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive)は、企業に対しバリューチェーン全体での人権および環境リスクの特定・対応を義務付けるもので、特にヨーロッパに拠点を持つ日本の製造業や商社に大きな影響を与えると考えられます。また、ドイツのサプライチェーン・デューデリジェンス法(2023年施行)や、フランスの注意義務法(2017年施行)も、企業に対しリスク評価および対策の実施を通じた情報開示を求めています。
CSDDDは、対象企業の範囲が段階的に拡大される予定で、中小企業への影響も今後注視する必要があります。(【解説】欧州企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の理解)
一方、米国では2022年にウイグル強制労働防止法(UFLPA)が施行され、中国・新疆ウイグル自治区の強制労働に関連する商品の輸入が禁止されています。これにより、日本企業も米国へ輸出する際には適切なデューデリジェンスを実施し、サプライチェーンの可視化を進めることが求められています。また、カリフォルニア州では2012年に「サプライチェーン透明化法」が施行され、一定規模以上の企業に人権デューデリジェンスに関する情報開示が義務付けられています。
UFLPAに関連して、米国当局は2023年以降、特定の業界に対する監視を強化し、特に衣料、電子部品、農産物などの分野では、企業の適切なリスク管理が求められています。これらの規制は、バリューチェーンの深い部分にまで影響を及ぼす可能性があるため、企業はサプライチェーン監査の強化が不可欠となっています。
*人権・環境デューデリジェンス(HREDD: Human Rights and Environments Due Diligence)は、企業が人権及び環境に関連する負の影響を特定・防止・軽減・是正するためのプロセス全般を指します。これは特定の法律や指令を指すも尾ではなく、概念や原則としてのフレームワークとなります。
日本企業の人権デューデリジェンス事例
近年、欧州や米国を中心に人権デューデリジェンス(DD)の法制化が進む中、日本企業も対応を強化しています。特に、グローバルなサプライチェーンを持つ企業は、取引先の人権リスクを特定・評価し、是正措置を講じることが求められています。
ここからは、日本企業の具体的な取り組みを紹介し、それぞれの企業がどのように人権リスク管理を強化しているのかを解説します。各企業は、自社の事業特性に応じたサプライチェーン分析やモニタリング体制の構築を進め、国際基準に則したリスクマネジメントを実践しています。
以下の表では、「サプライチェーン分析の活用方法」「人権DDの実施状況」「企業戦略としての人権リスク管理」の3つの視点から、代表的な日本企業の取り組みを整理しました。
| 企業名 | サプライチェーン分析の活用 | 人権DDの実施 | 企業戦略としての人権リスク管理 |
| 双日株式会社 | 国際NGOのデータベースを活用し、事業ごとのリスク分析を実施。外部専門家の慣習を受けて改善計画を策定。 | 事業分野ごとにリスク評価を実施し、統一的なCSRアンケートから個別分析へ移行。高リスクの取引先に改善対応を要求し、必要に応じて現地調査を実施。 | 「サプライチェーンCSR行動指針」を策定し、2050年までの長期ビジョン「サステナビリティチャレンジ」を掲げ、サプライチェーン全体での人権尊重を推進。 |
| キリンホールディングス株式会社 | 人権リスクマッピングを実施し、リスクの高い国・地域を特定。外部専門家の意見を取り入れてリスク管理を強化。 | 特定されたリスク地域において、現地訪問を行い、事業会社ごとの行動計画を策定。本社が進捗管理・モニタリングを担当。 | 経営戦略「CSV(Creating Shared Value)」の一環として人権を重要課題と位置づけ、人権方針を策定。サプライヤーガイドラインにも人権の視点を反映。 |
| 花王株式会社 | 国際NPOの情報共有プラットフォームを活用し、一次サプライヤーのリスク評価を実施。パーム油産業の人権リスクを特定し、トレーサビリティを強化。 | サプライヤーのリスク評価を実施し、基準を下回る場合は改善を要請。必要に応じて独自調査票を用いた追加評価も実施。 | 2011年の指導原則策定を契機に「花王人権方針」を策定・公表。ウェブ上に相談窓口を開設し、一般消費者からの通報も受付。 |
日本企業が直面する課題
日本企業の人権DDは着実に進展していますが、以下のような課題が依然として存在します(参考資料:JETRO、日弁連)
①データの可視化とトレーサビリティの難しさ
- 一次サプライヤーだけでなく、二次・三次サプライヤーまでのリスクや人権侵害の兆候を正確に把握する必要がある。
②コスト負担とサプライヤーへの影響
- 厳格な人権DDは、企業自体だけでなく取引先にも追加的な負担を与える。
- 特に中小企業ではリソース不足が問題となりやすく、対応が困難なケースも多い。
③各国法規制の変化に対応する柔軟性
- EUのCSDDDや米国UFLPAなど、法規制が頻繁に更新されるため、迅速な対応が求められる。
- 各国の基準に適合したコンプライアンス体制の整備が不可欠であり、継続的な情報収集と体制強化が求められる。
まとめ:人権デューデリジェンスの重要性と今後の対応
グローバル規制の強化により、日本企業もサプライチェーンおよびバリューチェーンにおける人権デューデリジェンスの実施が求められています。企業は、リスクの特定・評価を行い、サプライヤー管理を強化し、NGOや業界団体と連携して継続的な改善を進めることで、持続可能な経営を実現できます。特に、バリューチェーンの透明性確保とデータ活用が今後の重要課題となるでしょう。
日本企業は各国の規制に対応するだけでなく、バリューチェーン全体のリスク管理を強化し、透明性を確保することが競争力の向上にもつながります。持続可能な事業活動を実現するためには、サプライヤーとの連携やステークホルダーとの協働を強化し、国際基準に即した対応を継続的に進めることが不可欠です。
aiESGは、日本国内で初めて、サプライチェーンのESG影響を製品・サービスレベルで分析するツールを開発しました。これにより、企業活動をサプライチェーン/バリューチェーンの起点から製品生産段階まで精査することが可能です。
企業のサプライチェーン分析についてのご質問、疑問がございましたら、ぜひaiESGへお問い合わせください。
お問い合わせ:https://aiesg.co.jp/contact/
関連するaiESG記事:
【第一回】サプライチェーンが環境および社会に与える影響~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【第二回】学術、ビジネス、市民の三面の視点から主な推進要因とは~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【第三回】ステップ、対応、およびトレンド~持続可能なESG志向のサプライチェーン:現代ビジネスの戦略的必須条件~
【解説】欧州企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の概要と修正内容
【解説】欧州企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の理解:人権・環境に及ぼす悪影響を評価義務化
【解説】非財務情報開示における社会面の重要性
参考資料:
環境省 (2024), 「環境デューデリジェンスに関する取り組み事例集」
PwC (2024), 「人権・環境デューデリジェンスの法制化と日本企業が求められる対応」
JETRO(2023)、「人権デューデリジェンス、日本企業の対応は?」
JETRO(2023)、「陽性高まるグローバルな人権尊重対応(総論)」
HCDコンサルティング(2023)、「米国ウイグル強制労働防止法(UFLPA)によって、自動車部品やその原材料の輸入が差し止められ始めています」
外務省(2021), 「ビジネスと人権」に関する取組事例集
経済産業省 (2022), 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
ARC Watching (2020), 「人権尊重と環境デューデリジェンス」
環境省 (2018), 「バリューチェーンにおける環境デューデリジェンス入門」
日本弁護士連合会(2015)、「人権デュー・デリジェンスのためのガイダンス(手引)」